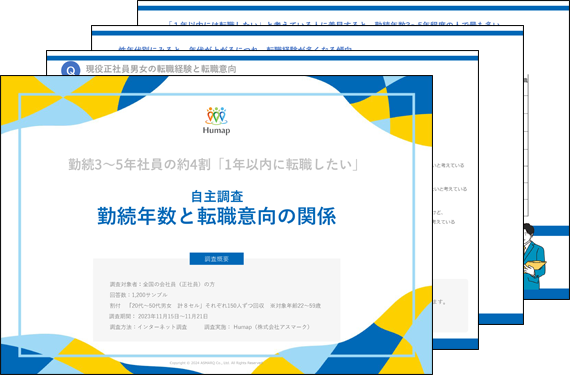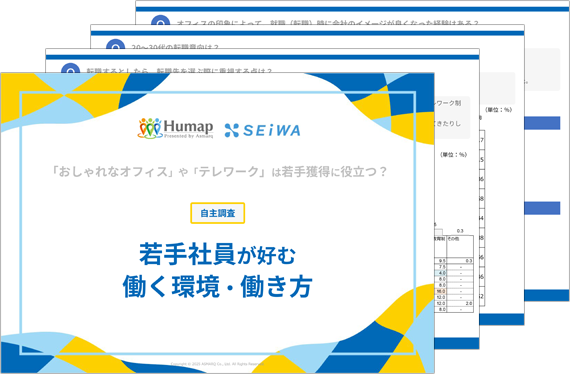採用ブランディングで人材を惹きつける方法|成功事例とメリットを解説

INDEX
この記事を読む方の中には「採用活動が非効率だが何をしたらよいか分からない」とお悩みの方がいるのではないでしょうか。 そこで今回は、採用ブランディングについてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
採用ブランディングとは?
採用ブランディングとは、組織のあり方や魅力、目指している姿を伝えて、入社への意欲を高めてもらうための取り組みのことです。未来を見越した事業展望に合う人材を採用するために実施します。採用ブランディングによって、自社の魅力を発信するとともに、既存の従業員が自社の価値を再確認できる場にもなっています。
採用ブランディングが注目される背景
採用ブランディングが注目されるようになった背景には、少子高齢化による人手不足と価値観の多様化、SNSの普及があります。
少子高齢化のため、優秀な人材の獲得が重要な課題です。とくに、勤続3~5年社員の4割が1年以内の離職を希望するなど、転職に対するハードルの低下が顕著であり、優秀な社員の流入を促す施策が重要視されるようになりました。
また、SNSの普及により、求職者は多くの情報を受信できるようになっています。ターゲットへ自社の魅力を確実に的確にアピールしなければ、求める人材の目に留まりません。 求める人材へ確実にアピールして応募意欲を高めるため、採用ブランディングが求められています。
採用ブランディングのメリット
採用ブランディングには、主に4つのメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
求める人材の応募者数の増加
採用ブランディングにより、求職者へ自社のコンセプトや魅力を伝えることで、ニーズに合った人材の応募の増加が期待できます。ともすれば面接をしてから「全く方向性が違った」といったミスマッチが減り、効率的な採用が見込まれるでしょう。
定着率の向上
求職者は、企業イメージを知ったうえで応募します。働き方や入社後の活躍が事前にイメージできていればミスマッチが起きにくく、入社直後の離職の回避につながります。また、既存の従業員に対しても採用ブランディングによって企業の魅力を再確認できれば、定着率の向上など好影響が見込めます。
企業の認知度が向上
採用ブランディングは、求職者の目に留まるだけではありません。広く発信しているため、求職者以外の目にも留まります。多くの目に留まることで、自社のファンが増えるとともに、認知度の向上が見込めるでしょう。
採用コストの削減
採用ブランディングにより、求職者のニーズと企業の求める人材のマッチ度が高い状態での応募が期待できます。
ニーズが合っていれば、内定辞退や早期離職のリスクは減り、結果的に採用効率の向上や辞退や早期離職による欠員募集の削減となるため、採用のコストカットにつながります。
長期的な目線では、自社への定着や愛着心が生まれることにより、友人を紹介するリファラル採用や、一度退職してカムバックするアルムナイ採用が見込まれるため、将来的な大幅なコストカットも期待できるでしょう。
採用ブランディングの成功事例
日本マクドナルドの成功事例をご紹介します。
言わずと知れたファストフードチェーン店です。同社は「ピープルビジネス」をコンセプトにブランディングしています。このコンセプトは、従業員へ企業が提供する価値を伝えることで、従業員が自発的にサービスを提供することを目指しています。 企業価値は、給与や福利厚生などの待遇だけでなく、ブランドや将来性など目に見えない部分の提供を重視しています。
参考:日本マクドナルド株式会社
採用ブランディングの進め方
採用ブランディングへの取り組みは、下記6つのステップを順に追って進めると良いでしょう。
1.自社の分析
最初に自社を再確認するために、次の項目における自社の魅力とマイナスポイントを洗い出します。
- 自社の強み
- 価値
- 業務内容
- 職場環境
- 人間関係
洗い出したら、他社と比較して優位性のある点や劣勢な部分をピックアップしておきます。
2.ターゲットとペルソナの設定
ターゲットは、求めるスキルやそのレベル、経験など求人の要件をまとめたものを指します。
ペルソナとは、より具体的な人物像です。具体的に人物像を設定すると、発信したいメッセージや伝え方のブレがなくなります。年齢・趣味・理想の転職先など、具体的にイメージしましょう。
3.コンセプトを決定
採用コンセプトは、活動にあたっての基本方針です。
コンセプトが不明確なまま採用活動を続けると、チャネルごとに発信メッセージが変わるなど、一貫性のない訴求になってしまい、求める求職者を採用しにくくなる可能性があります。 コンセプトは、中長期に渡って発信するため、5~10年後の事業展開や展望を経営層からヒアリングして取り入れるとよいでしょう。
4.アピールポイントの設計
アピールポイントとは、ターゲットとペルソナを受け入れてもらうために伝えるべき内容のことです。
例えば、次のようなペルソナと採用コンセプトを設定したとしましょう。
- 20代後半・論理的な考え方・キャリア志向が強い
- キャリアに関する情報とともに、業界研究や企業の情報も積極的に収集している
- 採用コンセプトは目指すは高み、挑戦の舞台
上記のような人物をターゲットに置いた場合、「挑戦」をコンセプトに置くことで、キャリア形成やスキルアップのイメージを求職者に与えることができるでしょう。
また、求職者は積極的に企業の情報収集することから、自社が取り組んでいる施策の紹介も有効になります。
例えば、組織体制の紹介として「権限を付与し自律的な行動を促している体制づくり」や「生産性向上」に関する施策の紹介をが適しています。
アピールポイントに迷う場合は、自社の魅力と市場のニーズを比較するのがおすすめです。理想の上司像やハラスメント対策など、あらゆる角度から自主調査を実施してきました。ぜひご活用ください。
5.発信内容と発信手段を決定
発信内容と手段は、アピールポイントに適していることが大切です。スキルアップの支援をポイントとする場合は、研修制度や評価制度の紹介、過去のプロジェクト例などを掲載するとキャリアアップをアピールできます。
手段とは、専用サイトやSNSなど、情報を発信する手法のことです。短い表現が魅力のXへ制度紹介を掲載すると、文字数が足りず、複数の投稿が必要なため、あまり適していません。このように、ポイントに応じた手段を選ぶのがポイントです。
6.効果測定と対策
採用ブランディングは、中長期的に取り組むべき施策です。次の採用に向けて、応募数や通過率などのデータを取得し、分析しておきましょう。また、入社した人材の人物像を把握するために、従業員アンケートや同じ部署のメンバーからヒアリングしておくと、採用ブランディングの効果が明確にできるでしょう。
使うチャネルの種類
ブランディングに使えるチャネルについてご紹介します。ニーズに合わせて適したチャネルを導入しましょう。
Webサイト
Webサイトは、採用サイト・オウンドメディア・ブログなどです。自社でメディアを作成して社員ブログを運営する手法も考えられます。自社で作成するため、自由度が高くイメージ像に近いサイト作成が可能な反面、自社のページを訪問した人のみの訴求となる点がデメリットです。自社サイトまでの誘導方法も検討が必要となります。
SNS
SNSは、X・Facebook・Instagramなどです。無料で始められるうえに利用者が多いので拡散力が高く、直接的なコミュニケーションがとれます。一方で、多くの利用者が投稿するため、目に留まる工夫や炎上しないためのルール作りが必要です。万が一の場合に備え、炎上対策も事前に準備することをお勧めします。
動画
近年は、動画で情報を発信する企業も増えています。YouTube・TikTokなど、発信内容に合わせて選びましょう。短時間で魅力を伝えやすい反面、企業ページの作成に高いコストがかかるうえに、表示回数を増やすためには発信数が重要となり、定期的な更新が必要となります。
イベント・ミートアップ
イベントは、合同会社説明会や座談会、ミートアップは共通の目的を持った人同士が集まる場所のことです。面と向かって直接魅力を伝えられる反面、長期的な構想でなければ採用効果を出すのが難しい場合があります。
求人サイト
求人サイトは、就職や転職を目的としてサイトを閲覧するため、採用効果の高さがメリットです。反面、掲載期間に応じて費用が高額になるうえに、競合他社も多く掲載しているため、比較される際に目に留まるよう構成やトピックを工夫したり、アピールの仕方も重要になります。最近は、求人サイトへ短時間の動画や自社の魅力を伝えるページなど、自由度の高いコンテンツも増えています。ニーズに合わせて取り入れてみてはいかがでしょうか。
自社の魅力を再確認するには「ASQ」
採用ブランディングとは、入社意欲を高めてもらうために自社の魅力をアピールする取り組みのことです。
少子高齢化や価値観の変化による人材不足が背景にあります。求める人材からの応募者数が増え、定着率の低下などが見込めます。
具体的な進め方は、6つステップで行います。まずは自社を分析してからターゲットとペルソナを設定し、コンセプト・アピールポイントを決めた上で発信内容とチャネルを決めていきます。最後に、効果測定をして長い目でブランドを育てていきましょう。
とはいえ、「自社の魅力がわからない」「何をアピールすべきか判断に迷う」などお悩みになる場合もあるのではないでしょうか。
自社の魅力を確認するには、従業員満足度調査がおすすめです。
アスマークの「ASQ」は、20年以上の調査歴を持つリサーチ会社の従業員満足度調査サービスです。従業員が感じている自社の魅力を可視化できたり、ベンチマークデータを保有しているため業界比較による強み・弱みを知ることができます。
レポートを見れば自社の魅力が分かる調査サービスです。 採用ブランディングを取り入れて、優秀な人材を多く獲得しましょう。
施策提言まで込みの
真に役立つES調査パッケージ
ASQ
執筆者

Humap編集局
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G