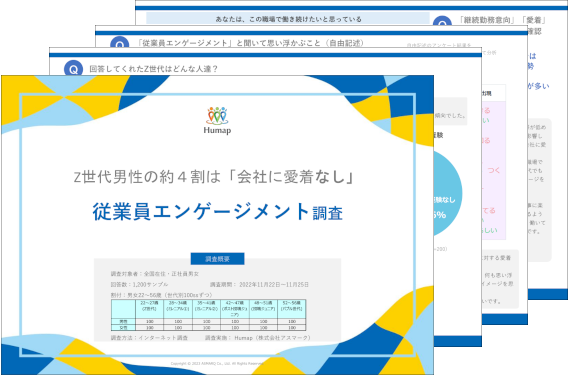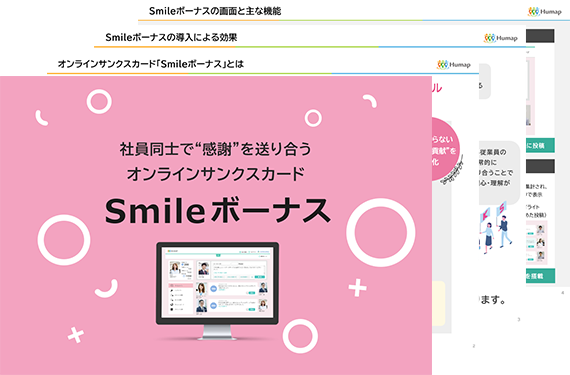SPIRE理論とは?エンゲージメント施策に活かす5つの視点と実践例

INDEX
組織における「社員の幸福度」や「エンゲージメント」が注目されるようになった背景には、働き方や価値観の多様化が大きく影響しています。特にリモートワークの普及により、従業員の「働く意義」や「つながりの実感」が問われる場面が増えるなど、これまで当たり前とされてきた職場のあり方にも見直しが求められるようになりました。
組織と個人の関係が大きく変わりつつある今、従来の「会社中心」「仕事中心」といった考え方を前提としない、柔軟な発想が求められています。社員が心身ともに健やかに働き、主体性を持って組織に関与できる環境を整えるためには、組織側の意識改革が欠かせません。それは結果として、持続的な成長や競争力の強化にもつながります。
この記事では、「SPIRE理論」の基本を押さえつつ、エンゲージメント向上を目的とした施策や研修への展開事例を紹介します。組織と個人の関係を見直し、本質的な職場づくりに取り組みたい方に役立つ内容です。
社員幸福度とエンゲージメントの重要性
近年、働き方改革やジョブ型雇用の導入などにより、企業を取り巻く労働環境は大きく変化しています。そうした中で注目されているのが、社員一人ひとりの幸福度とエンゲージメントです。
特にリモートワークや副業の普及は、従業員の「働く理由」や「職場への期待」の多様化を促進し、従来の管理型マネジメントの限界を浮き彫りにしています。
幸福度とエンゲージメント向上がもたらすメリット
- 離職率の低下:働きがいや心理的安全性の実感により、早期離職が抑制される
- 業績への好影響:主体的な行動や提案が増え、組織の生産性が向上する
- 職場の活性化:良好な人間関係が促進され、チームの連携力が高まる
- 採用力の強化:価値観や働き方を重視する応募者層にアピールできる
このように、社員の内面的な充実を起点とした組織づくりは、単なる福利厚生の域を超えて、経営戦略に直結する取り組みとして捉える必要があります。
また、心理的安全性の高い職場環境は、社員のメンタルヘルスを良好に保ちやすく、長期的な定着や安定したパフォーマンスにも寄与します。
SPIRE理論とは?社員幸福度を高める5つの要素
社員幸福度の向上に寄与する理論として注目されているのが、「SPIRE理論」です。これは、ポジティブ心理学の第一人者であるタル・ベン・シャハー氏が提唱した考え方で、人が持続的に幸福を感じるために必要な5つの要素の頭文字を取って名付けられました。
SPIRE理論の構成要素
- S(Spiritual:精神的な充実)→ 自分の価値観・生きがいを感じること
- P(Physical:身体的な健康) → 健康管理や運動習慣、休息の確保
- I(Intellectual:知的な成長) → 学びや挑戦、新しい体験への意欲
- R(Relational:良好な人間関係) → 職場・家庭・地域社会などのコミュニティでのつながり
- E(Emotional:感情の安定) → 自己肯定感やポジティブな感情の維持
これら5つの要素がバランスよく満たされる状態こそが、SPIRE理論が示す「ウェルビーイング」の基盤です。
特に職場環境においては、「Relational(人間関係)」と「Intellectual(成長機会)」が満たされない場合、エンゲージメント低下や離職リスクの上昇につながることが多いため、企業側の働きかけが不可欠となります。
仕事・職場環境での実践例
SPIRE理論の5要素は、職場環境づくりにおいても幅広く活用されています。たとえば「Relational(良好な人間関係)」を重視する企業では、部署を超えた対話の機会を意識的に設けたり、社員同士で感謝を伝え合う「サンクスカード」の運用を通じてつながりを促進するなど、企業によってさまざまな取り組みが行われています。
オンライン上で利用できるサンクスカードとしては、社員間の感謝を手軽に送り合えるサービス「Smileボーナス」があります。
幸福度とエンゲージメントの関係
社員幸福度とエンゲージメントは、どちらも組織のパフォーマンスに影響する重要な指標です。
- 社員幸福度:社員が「今この瞬間」に感じる満足感や幸福感
- 従業員エンゲージメント:社員が組織や仕事に対して持つ貢献意欲や愛着心
つまり、
- 幸福度が高まる → 心理的余裕が生まれ、前向きな働き方が可能になる
- エンゲージメントが高まる → 成果や達成感が得られ、幸福度も向上する
このように、両者は相互に作用し合う循環関係にあるため、SPIRE理論に基づいた施策とエンゲージメント施策を両輪で運用することで、より大きな効果が期待できます。
SPIRE理論を活用したエンゲージメント改善施策
SPIRE理論は、社員の幸福度を5つの側面から構造的に捉えるため、組織施策において実践的なフレームワークとして活用できます。エンゲージメントの向上にも直結する要素が多いため、注目されています。
▼ SPIREを取り入れた具体策
- S(Spiritual):経営理念やビジョンを社員と共有する場を設ける
- P(Physical):リフレッシュ休暇や健康支援制度の導入
- I(Intellectual):社内研修・外部講座・キャリア面談の実施
- R(Relational):1on1ミーティング・社内イベントの強化
- E(Emotional):日報や朝礼でのポジティブフィードバック習慣
これらの施策を個別に展開するだけでなく、組織全体でバランスよく整備することが、社員のウェルビーイングとエンゲージメントの底上げにつながります。
企業研修で幸福度とエンゲージメントを高める方法
社員の幸福度やエンゲージメントを高めるには、企業研修のあり方も見直す必要があります。
単に知識を習得する場としてではなく、「自分の存在が認められ、成長を実感できる場(自己肯定感の醸成)」や「組織とのつながりの実感」といった内面的な要素に着目した研修設計をすることで、心理的な満足度と仕事への前向きな意欲を引き出せます。特に、SPIRE理論が示す5つの要素(精神・身体・知性・関係性・感情)を意識したプログラム設計は効果的です。
幸福度・エンゲージメントを高める研修例
- メンタルヘルス研修(精神・感情)
- リモートワーク下でのコミュニケーション研修(関係性)
- キャリアビジョン設計ワークショップ(知性・感情)
- 社内表彰制度との連動型研修(感情・関係性)
- フィジカルヘルス講座・健康習慣づくり(身体)
幸福度とエンゲージメントの向上には、研修の質と内容の工夫が大きく影響します。企業の理念や目指す組織像に合わせ、SPIREの観点からバランスよくプログラムを組むことがポイントになります。
コミュニケーションの見直し
エンゲージメントや幸福度の向上において、「Relational(良好な人間関係)」の充実は欠かせません。日々のコミュニケーションの質を高めることで、心理的な充足感や安心感が生まれやすくなります。 特にハイブリッドワークが広がる現在では、業務連絡だけでなく、気軽な声かけや非業務的な対話の機会をどう作るかが重要なテーマといえます。
例えば、出社・在宅・外出・休暇などの勤務状況をリアルタイムに可視化できる座席管理ツール「せきなび」を導入することで、対面の有無にかかわらず社員同士のつながりを維持しやすくなります。ハイブリッドワークやフリーアドレスなどの導入によって、社内のコミュニケーションに課題を感じている場合は、こうしたツールの導入も検討されてみてはいかがでしょうか。
テレワークでも出社でも、
在席管理ツールなら
せきなび
成功事例に学ぶエンゲージメント施策の効果
社員のウェルビーイングを高めるには、まず現状を可視化することが重要です。従業員の心身の状態や職場環境に対する満足度をサーベイによって把握し、そこから具体的な施策につなげていく企業も増えています。
ここでは、SPIREの視点に通じる多面的な取り組みを、実際にサーベイを起点として展開している企業の事例として紹介します。
株式会社アシックス
アシックスでは、従業員の心と身体の健康を基盤とした「ウェルビーイング経営」を推進しています。全社員を対象としたウェルビーイングサーベイ(ASICS Well-being survey)を全社員に実施し、身体的・精神的・社会的な健康状態を可視化。得られたデータに基づき、社内外の専門家と連携した健康増進施策や、メンタルヘルス支援、運動促進プログラムなどを継続的に展開しています。
楽天グループ
楽天では、従業員のウェルビーイングを企業の持続的成長を支える重要な要素と位置づけ、全社的な取り組みを進めています。定期的なウェルビーイングサーベイを通じて、心身の状態や職場環境に対する満足度を把握し、分析結果に基づいた施策を展開。社内診療所の設置、運動プログラム、オンライン相談窓口など、SPIREの複数要素を包括する支援体制を整えています。
参考:従業員のウェルビーイング向上に向けた取り組み|楽天グループ株式会社
従業員エンゲージメントを可視化する方法
エンゲージメントを高めるには、まず現状を可視化することが不可欠です。社員が今、どの程度「会社に貢献したい」と感じ「仕事にやりがいを見出しているか」を数値や定性データで把握することが、効果的な施策設計の出発点となります。可視化の具体的な方法としては、以下のような手法が活用できます。
- 従業員サーベイ(アンケート):定期調査によって満足度やエンゲージメント度を計測
- 1on1面談:個別面談で本音をヒアリングし、数値化しにくい要素も把握
- ES(従業員満足度)調査ツール:オンラインで状況を可視化し、傾向を分析
| 手法 | 特徴 | 活用シーン |
| 従業員サーベイ | 数値化しやすく、全体の傾向がつかめる | 毎月~四半期ごとの実施 |
| 1on1面談 | 本音や背景を深掘りできる | 月1~隔月で定期面談 |
| ES調査 | データの蓄積・推移分析がしやすい | 半期・年度ごとの実施 |
なお、こうした手法は自社で実施することも可能ですが、調査設計や分析には相応のリソースや専門知識が必要となるため、外部委託を検討する企業も少なくありません。
「ES+」で課題把握と改善へ
当社の「ES+(イーエスプラス)」は、社員の幸福度やエンゲージメントの状態を多面的に測定し、課題の可視化と、最適な研修プランの設計までサポートするサービスです。独自の分析手法で組織の強みや弱みを明確にし、改善ポイントを具体的に示します。
【 ES+の主な特徴 】
- 精度の高いサーベイと回答分析
- 調査歴20年のプロが設計した独自の評価指標
- 部門別・属性別の詳細レポートの提供
- 改善アクションや最適な研修プランの提案
- 導入後のフォローアップ体制も充実
このように、ES+を活用することで、社員の声を的確に把握し、課題解決に向けた施策のPDCAを継続的に回していくことができます。
社員の幸福度とエンゲージメントの向上は、組織の成長と安定に欠かせない要素です。自社に合ったアプローチを選定し、継続的な改善サイクルを通じて、誰もが前向きに安心して働ける職場づくりを目指していきましょう。
「調査+研修」で
働きやすい職場環境づくりを
ES+
執筆者

Humap編集局
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G