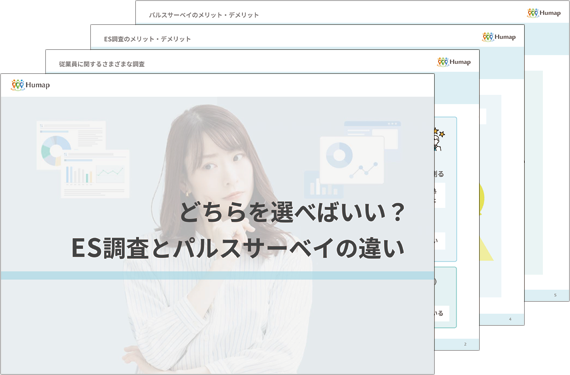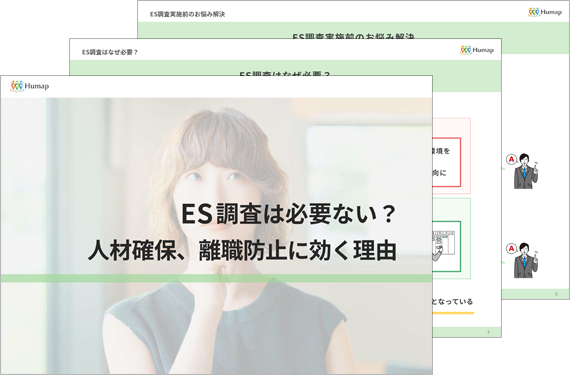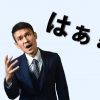なぜ若手社員は退職代行を使うのか?利用増加が示す従業員満足度の低下と改善ステップ

INDEX
はじめに:退職代行利用の急増と若手社員の離職課題
この記事をご覧の方の中には、「退職代行の利用増加」や「若手の離職」に対して、危機感をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
近年、20代〜30代を中心に「退職代行サービス」の利用が増えています。
企業にとっては、従業員満足度(ES: Employee Satisfaction)の低下や離職率の上昇が経営リスクとして顕在化しており、早期の対策が求められています。
この記事では、退職代行が増加する背景や、ES調査を通じて従業員の本音を可視化し、定着率低下の要因を把握したうえで改善につなげるためのポイントを解説します。
退職代行サービスとは?なぜ若手に支持されるのか
まずは退職代行サービスの仕組みと、若手層から支持を集める理由を整理しておきましょう。
退職代行サービスの定義と仕組み
退職代行サービスとは、従業員に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスです。主に以下の形態があります。
- 弁護士型:弁護士が経営。法的交渉が可能で、費用の目安は5~10万円
- 民間業者型:一般企業が運営。連絡代行のみで費用の目安は3~5万円
若手層に支持される背景
では、なぜ退職代行サービスは若手層から支持されているのでしょうか。背景には、以下のような事情があります。
- 上司や会社に直接「辞めたい」と言いにくい心理
- パワハラ・モラハラなどハラスメントへの懸念
- 精神的負担を避け、確実に辞められるという安心感
特に新卒や若手社員はキャリア経験が浅く、交渉スキルや心理的な耐性が十分ではないことも少なくありません。そのため、退職手続きに第三者の力を借りる選択肢が広がっていると考えられます。
若手が抱える期待と現実のギャップ
若手社員の離職背景を理解するには、ES調査を通じて「期待」と「不満(現実)」のギャップに注目する必要があります。どのようなギャップが考えられるのか、具体的な例を挙げていきます。
若手から見えるギャップ例
- キャリアアップへの期待 vs. 成長機会の不足
- ワークライフバランス志向 vs. 労働時間の長さ
- 公平なフィードバックへの期待 vs.不透明な評価制度
- 心理的安全性のある職場 vs. 人間関係の摩擦
ES調査の回答などから、次のようなサインが多くみられる場合は、注意が必要です。
■チェックリスト(若手の不満サイン)
- 「入社前の期待とのギャップが大きい」と回答する社員が多い
- 「評価が不公平」という声が多い
- 「成長実感がない」と回答した社員の割合が高い
ES調査を活用した離職防止・定着率向上のプロセス
ES調査を単なる満足度調査で終わらせず、離職防止に結びつけるには、段階的な活用プロセスが有効です。
ステップ1:目的の明確化と仮説設定
「若手の早期離職率の低下」や「新卒3年以内の満足度向上」など具体的な目的を据え、その達成に関わる要素(勤務時間・成長機会・上司との関係性など)を仮説として設定します。
ステップ2:設問設計と実施準備
離職要因を踏まえた設問を設定し、匿名性を担保した形式で調査を実施します。入社前とのギャップ、キャリアパス、評価制度、柔軟な働き方などを確認する設問が効果的です。
ステップ3:分析と課題抽出
部署別・年次別にクロス集計を行い、若手層の特徴的な傾向を把握します。また、自由記述から定性的な「本音」を抽出することも重要です。
ステップ4:改善施策の立案と実行
ステップ1〜3の結果に沿って、具体的な改善施策を検討します。
例:フィードバック制度の改善、キャリアパスの可視化、業務量の適正化、育成プログラムの導入など
各施策の責任者と、期限を定めて実行することがポイントです。
ステップ5:フォローアップと定着評価
パルスサーベイを活用した日々のスコアを可視化したり、従業員調査を半年に1回など定期的に実施し、離職率やESスコアの改善度を測定します。結果を社員にフィードバックすることで、社員との信頼関係も強化されます。
退職代行に至る前に押さえる若手離職のサイン
離職する若手社員には、「退職代行を利用する」という選択を取る前段階として、必ず何らかのサインが現れるものです。人事担当者は、その兆候を見逃さないような仕組みを整える必要があります。
若手離職リスクのサイン一覧
従業員満足度調査の回答から、退職リスクの兆候を読み取ることができます。
- 「入社前とのギャップが大きい」と回答している
- 人事評価や教育制度に対して強い不満を持っている
- 上司・先輩とのコミュニケーションが少ない
- 勤務時間や休日、休暇制度への不満
- 成長実感が乏しく「キャリアが見えない」状態
部署別や年次別に分析することで、リスクの高いグループを把握し、早期に対策を打つことも可能となります。
また、定期的に調査を行い、目標に対する部署ごとの改善状況や変化を経年比較することも有効です。
企業が取るべき施策:満足度を高め、退職代行利用を防ぐ
早期のサインに対応し、具体的な改善策を講じることで、退職代行の利用を未然に防ぎ、若手社員の定着率を高めることが期待できます。
実践施策の例
- 1on1面談や定期的なキャリア相談制度
- OJT・メンタリング体制の強化
- テレワークや時短勤務など柔軟な働き方の導入
- 成果・評価基準の透明化
- リフレッシュ休暇や健康支援など福利厚生の充実
- 職場環境改善(休憩スペースや設備整備)
- 上司のリーダーシップ強化と心理的安全性の醸成
まとめ:ES向上を通じて退職代行を未然に防ぎ、組織力を強化
ここまで、退職代行利用急増の背景、若手視点でのES(従業員満足度)のギャップ、調査を活用した改善プロセス、そして実践施策を整理しました。重要なのは、「待ち」の姿勢ではなく積極的に従業員の声を吸い上げ、見える化し、改善につなげるサイクルを確立することです。
ES調査と離職防止支援
アスマークの「ASQ(アスク)」は、従業員満足度を測るだけでなく、組織の課題点をあぶり出し、施策提言までが付いた調査サービスです。
- 企業の課題に合わせた設問設計
- 従業員の満足度と離職意向について多面的に分析
- 改善施策の立案サポートとフォローアップ
ASQを活用することで、若手社員の不満や離職リスクを早期に可視化し、退職代行に至る前に改善アクションを打つことが可能となります。
結果として、ESスコアの向上や離職率の低下、若手社員のモチベーション維持につなげることが期待されます。
またアスマークでは、さらに「若手の離職防止」に特化した調査を実施できる、課題別調査パッケージ「ES調査ライト」も提供しています。
満足度が下がった若手社員が退職代行の利用に至る前に、従業員の声を可視化し、離職防止に役立てていきましょう。
施策提言まで込みの
真に役立つES調査パッケージ
ASQ
執筆者

Humap編集局
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G