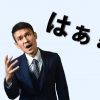アンダーマイニング効果を防止する5つの戦略|原因と影響も解説

INDEX
この記事をご覧の方の中には、
「突然、意欲が減退した従業員がいるが、どのように対応すべきかわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
今回は、“アンダーマイニング効果”の原因と防止策について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
アンダーマイニング効果とは
アンダーマイニング効果とは、探求心や好奇心、達成感など内的な要因で行動していた人が、報酬を与えられることで「見返りがなければ意味がない」と考えるようになり、やる気が低下する現象を指します。仕事の目的として報酬は重要な要素ですが、報酬を与えるタイミングや方法は考える必要があります。
内発的動機づけ・外発的動機づけとは
動機づけとは、行動を維持するための目的やきっかけのことです。動機づけには、報酬や評価など外部要因による「外発的動機づけ」と、達成感や探求心、好奇心など内的要因による「内発的動機づけ」があります。
どちらもやる気を引き出すために重要な要素ですが、内発的動機づけを保てていれば、強いモチベーションの維持につながります。一方で、外発的要因によって内発的動機が弱められると、アンダーマイニング効果が発生します。
アンダーマイニング効果の実証実験
アンダーマイニング効果は、1971年にアメリカの心理学者マーク・R・レッパーとエドワード・L・デシが行った実験によって実証されました。実験は、対象者を2つのグループに分け、次のような流れで行われました。
- 1. 両グループにパズルを渡す
- 2. パズルを解いたら、Aグループには報酬を与え、Bグループには何も与えない
- 3. 再びパズルを解いてもらう
その結果、報酬を与えられたAグループは、何も与えられなかったBグループよりもパズルに触れる時間が短くなりました。はじめは好奇心から取り組んでいた行動が、「報酬を得るための手段」に変化したと考えられます。
エンハンシング効果
アンダーマイニング効果とは対照的なものとして、エンハンシング効果という現象があります。賞賛効果とも呼ばれ、外発的要因によって内発的動機づけが高まり、意欲を向上させる効果を指します。たとえば、仕事ぶりを周囲から褒められたことで、意欲が増してより力を発揮できた、といった状況があげられます。この効果を適切に活用すれば、見返りを求めないモチベーションを引き出すことができると考えられます。
従業員の意欲を引き出し、生産性を高めるマネジメント手法についてまとめた資料も公開しています。こちらもぜひご参照ください。
アンダーマイニング効果の要因
アンダーマイニング効果が起こる主な要因は以下の3つです。
1.行動の目的が内発的から外発的に変わる
報酬を与えられると、内発的な動機よりも報酬を気にするようになり、報酬が目的となることで意欲が低下します。
2.自己肯定感の低下
内発的動機づけによって行動しているときは、自らの意志によって行動をコントロールしている実感がありますが、報酬が与えられることによって「やらされている感」が増し、自己肯定感の低下につながると考えられます。
3.締め切りやノルマの存在
外発的動機づけとして締め切りやノルマがあることは、短期的には意欲を向上させても長続きしづらい傾向にあります。
アンダーマイニング効果が与える影響
アンダーマイニング効果が起こると、企業と従業員にどのような影響を与えるのでしょうか。
企業への影響
- 離職者の増加
- 生産性の低下
- 事故リスクの増加
意欲が減退し、仕事への興味が薄れた従業員は、離職を考えるようになります。意欲のない状態で仕事を進めているため、組織全体の生産性が低下します。加えて、集中力が散漫になることで、大きなミスや事故のリスクも増加することが懸念されます。
従業員への影響
- 人間関係の悪化
- モチベーションの向上が難しい
成果報酬制度は従業員間の競争を促す効果がありますが、人間関係の悪化を引き起こす可能性も併せ持っています。また、一度アンダーマイニング効果によってモチベーション低下が起きると、一度下がってしまったモチベーションを内発的要因によって再び回復させることは困難です。一時的に報酬を上げたとしても、高い意欲を維持させることは難しいでしょう。
アンダーマイニング効果を防ぐ5つの施策
アンダーマイニング効果を発生させないために、企業はどのような対策を取るべきでしょうか。5つの施策をご紹介します。
モチベーションへの理解を深める
モチベーションがどのように変化するのか、そのメカニズムを理解することで、やる気の維持につながります。たとえば、以下のようなモチベーション理論を参考にするとよいでしょう。
2要因理論:
満足をもたらす要因(動機づけ要因)と、不満足をもたらす要因(衛生要因)は別々のものであるとする理論。
マズローの欲求5段階説:
人間の欲求を5段階の階層で理論化したもの。生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求という5段階の欲求があり、生理的欲求から順に満たされていくことで、最終的に自己実現欲求に至ると考えられる。
このような理論を活用することも、従業員の意欲を引き出す環境づくりのヒントになります。
簡単な目標を設定する
簡単に達成できる目標を設定することで、達成感を得やすくなり、自己肯定感が向上します。達成感を得ることで自信を持つことができ、内発的動機づけを高めるきっかけとなります。長期的な目標も、スモールステップに分けて設定することで効果的に進められます。
現金以外の報酬を導入する
金銭を報酬にすることは、限界がある上に、報酬が目的化しやすくなるため、別の方法を検討してみましょう。たとえば有給休暇の増加、育児手当の導入、福利厚生の充実など、金銭以外の報酬には内発的動機を高める効果があります。金銭以外の報酬によって従業員の生活そのものが充実すると、仕事に対する満足感が増すことが期待できるでしょう。
自律的な行動を促す
細かく指示を出すと、「やらされている感」が増してモチベーションが低下します。細かい指示出しは避け、意思決定の自由度を持たせることで、従業員の自己肯定感を高めることが大切です。自律的な行動が増えるほど、内発的動機づけが促進されるでしょう。
ほめ方を工夫する
エンハンシング効果を活用して従業員のやる気を高めることも効果的です。ただし、適当に褒めるだけでは効果がありません。一人ひとりの具体的な行動や成果に焦点を当てて賞賛を伝えましょう。ほかの従業員の前で褒めることや、非言語的な表現(ジェスチャーや表情)を交えると、さらに効果的です。
日常的に感謝を伝える取組みも効果的です。たとえば、感謝や賞賛を送り合えるピアボーナスという制度があります。
Humapの「Smileボーナス」のようなツールを活用することで社内コミュニケーションが活性化し、モチベーションの向上にもつながります。
感謝を伝えあえる
オンラインサンクスカード
Smileボーナス
モチベーションの把握でアンダーマイニング効果を抑止
従業員の意欲や気持ちが変化する要素を把握するためには、定期的な従業員満足度調査の実施が有効です。調査によって意欲が変化する要因を可視化できるため、早期の課題解決につながります。
モチベーションの把握には「ASQ」
「ASQ(アスク)」は、従業員満足度を測る調査サービスです。従業員のやる気に影響する要因を、満足度や離職意向と合わせて分析することで、解決すべき課題が明確になり、従業員のモチベーションを高めるための具体的な施策が見えてきます。
アンダーマイニング効果の発生を未然に防ぎ、従業員の意欲を持続させ、生産性を高めるための取組みとして、「ASQ」の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
施策提言まで込みの
真に役立つES調査パッケージ
ASQ
執筆者

Humap編集局
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G