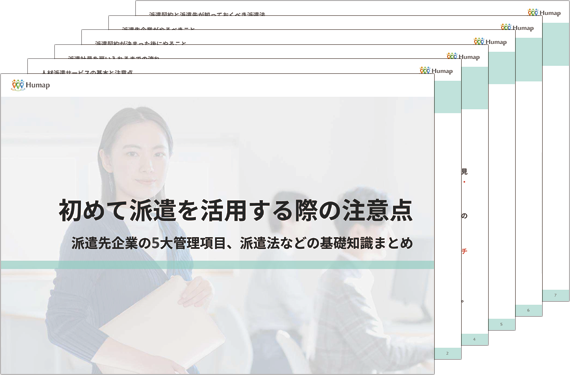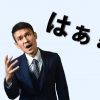【ニーズ別】採用方法16種類を徹底比較!成功のためのポイントも解説

INDEX
採用活動において、「採用広告を出しても応募者が少ない」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、16種類の採用方法と、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。自社のニーズに合った採用方法を見つけるための参考にしてください。
採用方法一覧
2025年3月現在、企業の採用方法は主に16種類あります。各採用手法の特徴を理解し、募集要件や自社の状況に応じて最適な方法を選択しましょう。

低予算の採用方法
採用コストを抑えたい場合に適した方法は、以下の6種類です。
1.ハローワーク
- 特徴:ハローワークに求人を掲載
- メリット:無料で長期間掲載できる
- デメリット:魅力を伝えにくい、ミスマッチが起きやすい
ハローワークは、厚生労働省が管轄する公的なサービスで、求人掲載は無料です。一定の要件を満たせば助成金や給付金の対象となる場合もあります。一方、求人票の文字数制限があるため、自社の魅力を十分に伝えにくい点が課題です。また、誰でも応募ができるため、想定外の求職者からの応募が増え、ミスマッチが起きやすい点がデメリットといえます。
2.自社Webサイト(オウンドメディアリクルーティング)
- 特徴:公式サイトの採用ページや、専用サイトを開設
- メリット:自社の魅力を最大限に伝えられる
- デメリット:広範囲へのアプローチが難しい
自社Webサイト内に採用ページを設ける、または専用サイトを開設して募集します。サイト構築と運用のコストは発生しますが、デザインや動画、社員インタビューなどオウンドメディアならではの豊富なコンテンツを駆使して自社の魅力を求職者にアピールすることができ、長期的に見ると低コストで済みます。しかし、求職者が自社を認知していない場合は、訪問される機会が少なく、単体で不特定多数にアピールすることは難しいといえます。
3.ソーシャルリクルーティング
- 特徴:SNSを活用し、求職者に情報発信・直接やり取りを行う
- メリット:無料で広範囲に情報を発信できる
- デメリット:運用に手間がかかり、担当者の負担が多い
XやLinkedInなどのSNSを利用して企業の魅力を広く発信し、求職者と直接コミュニケーションを取る方法です。コストをかけずに広範囲へアプローチできる一方で、求職者の目にとまるためには継続的・定期的な投稿が必要となるため、運用負担が大きい点が課題です。SNSの運用と自社サイトを組み合わせてブランディングできると、高い効果が期待できます。
4.リファラル採用
- 特徴:従業員の紹介による採用
- メリット:中小企業でも優秀な人材を確保しやすい
- デメリット:応募数が安定しない
リファラル採用は、従業員からの紹介で採用を行う方法です。他の方法に比べて低コストで済み、知名度の低い中小企業やベンチャー企業でも優秀な人材を獲得できる可能性があります。従業員を介して職場の雰囲気や企業文化などをある程度理解した状態で応募するため、ミスマッチを防ぎやすい点がメリットです。しかし、従業員が紹介できるタイミングに依存するため、いつ応募がくるか分からず、大人数の採用や計画的な採用には不向きです。紹介制度を整備し、従業員が積極的に紹介・推薦できる環境を作ることが成功のポイントになります。
5.【新卒のみ】大学就職課
- 特徴:大学の就職課に求人を無料で掲載
- メリット:大学の特徴を踏まえた人材採用が可能
- デメリット:応募数が予測できない
大学の就職課に無料で求人を掲載してもらう方法です。特定の大学に向けた採用活動が可能で、大学の特徴から求職者のイメージがつかみやすい反面、企業側が応募を待つ形になるため、何名ぐらいの応募がくるのか事前に予測することはできません。定期的に大学へ足を運び、就職課の担当者と良好な関係を築くことで、優秀な学生を紹介してもらえる可能性が高まります。
6.オフィスの掲示物
- 特徴:店舗やオフィス前などに求人情報を掲示
- メリット:無料で長期間掲載できる
- デメリット:広範囲へのアプローチが難しい
オフィスの掲示物は、近隣の求職者に向けた採用方法として有効です。特に、パートやアルバイトの募集には適しています。コストがかからない反面、通りかかって気づいた人にしか目に入らないため、広範囲へのアピールには向いていません。認知度を高めるには他の手法との併用が必要です。
スピード重視の採用方法
急な退職などで欠員補充が必要になり、採用スピードを重視する場合に適した採用方法は、以下の3種類です。
7.求人広告
- 特徴:求人広告を掲載(紙・Web・アプリなど媒体の種類が豊富)
- メリット:一度に多くの求職者にアピールできる
- デメリット:掲載費用が高額
求人広告は、幅広い求職者に情報を届ける手段として有効です。要件を問わず広く掲載するものと、地域密着型の媒体や業界・業種に特化した媒体があるため、自社に適した媒体を選択することで、より早く人材を確保できる可能性が高まります。ただし、掲載期間が限られており、掲載料がかかるため、費用対効果を考慮する必要があります。
8.合同企業説明会(転職フェア)
- 特徴:転職フェアや合同企業説明会に出展する
- メリット:求職者と直接会って話すことができる
- デメリット:準備の負担が大きく、高額な出展費用がかかることも
合同企業説明会は、求職者と直接会える点がメリットです。企業の魅力を直接伝え、質疑応答により求職者が企業理解を深める場としても有効です。転職フェアでは、その場で面接を行ったり、内定を出したりすることが可能な場合もあります。一方で、出展コストが高く、事前準備も必要なため、結果によっては費用対効果が見込めない可能性もあります。
9.人材派遣
- 特徴:派遣会社に依頼して人材を確保
- メリット:短期間で人材を獲得でき、直接雇用の道も
- デメリット:自社にノウハウが残りにくい
自社雇用ではないものの、即戦力が求められる場面において、一時的に人材を確保する方法として有効です。希望するタイミングで人材を獲得できるほか、直接雇用の可能性もある点はメリットですが、基本的には期間の制限内での雇用となるため、派遣スタッフの知識やスキルが社内に蓄積されない点には注意が必要です。
人材派遣の利用を検討されている方は、下記の資料もぜひご活用ください。
ミスマッチの少ない採用方法
求職者と企業の相性を事前に確認し、ミスマッチを少なくする採用方法は、以下の4種類です。
10.インターンシップ
- 特徴:採用前の職業体験を実施
- メリット:事前に求職者の適性を確認できる
- デメリット:準備の手間と、採用までの時間がかかる
選考前に職場体験をしてもらうインターンシップは、求職者の適正と相性を確認できる点が大きなメリットです。特に新卒採用では定着率の向上につながるため、人材戦略の一環としてインターンシップを取り入れている企業もあります。ミスマッチが少なく、効率的な採用が実現できる一方で、準備の手間と採用までの時間がかかるため、導入のハードルはやや高めです。基本的には新卒を対象とした方法ですが、近年は中途採用でも実施する企業もあるようです。
11.アルムナイ採用
- 特徴:過去に自社を退職した人材を再雇用する方法
- メリット:企業文化を理解しており、即戦力になりやすい
- デメリット:応募数が不透明で、大量採用には不向き
退職者を再雇用するアルムナイ採用は、採用コストをかけずに、企業の文化や業務に精通した人材を獲得できます。即戦力として活躍しやすいことが特徴ですが、退職者の意向に左右されるため、採用につながるケースは少なく、計画的な採用や大量採用には不向きです。退職前から良好な関係を築いておくことがアルムナイ採用を成功させるポイントになります。
12.カジュアル面談
- 特徴:応募前に求職者と企業が対話できる面談を行う
- メリット:優秀な人材と早い段階で接点を持てる
- デメリット:必ずしも採用に直結しない
カジュアル面談は、応募前の求職者と企業が対話し、相互理解を深める場です。一般的には応募前に、合否に関係なく実施します。優秀な求職者と早い段階で接点を持てる点がメリットですが、まだ志望を決めていない求職者であることが多いため、すぐに採用につながるとは限りません。長期的な関係構築を目的とした運用が求められます。
13.ミートアップ採用
- 特徴:食事会や交流イベントを通じて企業をアピールする場
- メリット:転職を考えていない潜在層にもアピールできる
- デメリット:準備に手間がかかり、採用に直結しにくい
ミートアップ採用は、食事会や一緒にゲームをする交流イベントなど、カジュアルな場によって企業の魅力をアピールし、求職者と関係を築く手法です。転職予定のない潜在層へアピールできる点がメリットですが、直接的な採用にはつながりにくく、準備の手間もかかるため、費用対効果の見極めが必要になります。
高スキルや管理職向けの採用方法
高い専門スキルや管理職を採用する際に適した方法は、以下の3種類です。
14.人材紹介
- 特徴:紹介会社に人材を紹介してもらう
- メリット:手間をかけずに即戦力を採用できる
- デメリット:成功報酬が高額
人材紹介会社に要件を伝えて、即戦力となる人材を紹介してもらう方法です。希望に合った候補者の紹介や面接日程、条件交渉、内定承諾に至るまでのやりとりを紹介会社が行い、採用に至れば成功報酬を支払います。手間をかけずに希望の人材を獲得できる反面、中途採用では年収の30%~45%、新卒採用では100万円前後と、成果報酬として高額なコストが発生する点がデメリットです。
15.ヘッドハンティング
- 特徴:スカウト型と登録型の2種類がある
- メリット:優秀な人材を獲得しやすい
- デメリット:成功報酬が高額
ヘッドハンティングは、企業が積極的にアプローチをして他社から優秀な人材を獲得する手法です。方法としては、ヘッドハンティング会社が持つデータベースからターゲットを指定してスカウトする「スカウト型」と、転職エージェントに登録されている人材から探す「登録型」の2種類があります。特に専門性が高い職種やエグゼクティブ層の人材獲得に向いている反面、採用コストが高額になりやすい点がデメリットです。
16.ダイレクトリクルーティング
- 特徴:転職エージェントに登録している人材をスカウト
- メリット:企業が触接、希望する人材にアプローチできる
- デメリット:個別対応の手間がかかる
ダイレクトリクルーティングは、転職エージェントに登録されている人材を、企業が直接スカウトする手法です。希望の人材にターゲットを絞って直接アプローチできるため、マッチ度の高い候補者を獲得しやすい反面、求職者が応募するとは限らず、スカウト送付や個別対応の手間が多いため、担当者に負担がかかる点がデメリットです。
このように多くの採用方法がある中で、自社にとって本当に必要な人材を見極めるためには、会社のどこにどのような課題があるのか、現状を正しく理解した上で人材戦略を立てる必要があります。そこで、課題を把握するために有効なのが、従業員満足度調査です。
自社に合った採用方法を選ぼう
16種類の採用方法について、特徴、メリット・デメリットを解説しました。
- コストを抑えたい→ハローワーク、自社サイト、ソーシャルリクルーティング、リファラル採用、大学の就職課、オフィスや店舗の掲示物
- スピード重視→求人広告、合同企業説明会、人材派遣
- ミスマッチを防ぐ→インターンシップ、アルムナイ採用、カジュアル面談、ミートアップ採用
- 高スキル・管理職向け→人材紹介、ヘッドハンティング、ダイレクトリクルーティング
採用活動の前に、自社の人材課題を正しく把握し、重視するポイント(コスト、スピード、マッチ度、スキル)を見極めた上で、最適な手法を選びましょう。
手間をかけずに自社の特徴をつかむには「ASQ」
採用活動を成功させるためには、自社の強みや課題を正しく把握することが不可欠です。しかし、社内での調査には時間と手間がかかるため、客観的、かつスピーディーに現状を可視化できる手段が求められます。
「ASQ」は、調査会社として20年以上の実績を持つアスマークが提供する従業員満足度調査サービスです。ヒアリングから設問設計、アンケート実施、分析まで行い、調査結果を見やすいレポートで提供。従業員の声をもとに、自社の特徴を可視化し、貴社に最適な採用戦略の立案につなげます。
最適な採用方法を選択するために、従業員満足度調査の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
施策提言まで込みの
真に役立つES調査パッケージ
ASQ
執筆者

Humap編集局
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G