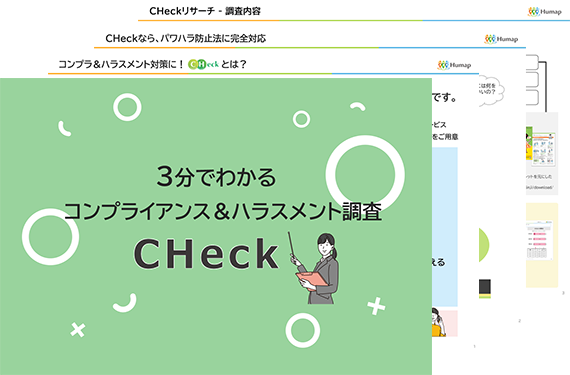派遣社員の副業はOK?企業・従業員が注意すべきポイントを解説

この記事を読む方の中には、「副業を希望する派遣社員に対して、どのような点に注意すべきか?」とお悩みの方がいるのではないでしょうか。
今回は、派遣社員の副業について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
派遣社員の副業は可能?
派遣社員の副業は、法律上禁止されていません。ただし、企業の就業規則により副業を制限されるケースがあります。副業を禁止するのは、次のような理由からです。
- 本業に支障をきたす可能性がある
- 企業の機密情報が漏えいするリスクがある
就業規則で副業を禁止することは合法であり、就業規則で副業が禁止されている場合、原則として副業は認められません。派遣社員が副業を希望している場合は、派遣会社および派遣元企業の就業規則を事前に確認しておきましょう。
副業を始める前に知っておくべきこと
副業をはじめようとする際、派遣社員が知っておくべき重要なポイントがあります。
- 確定申告
- 住民税
- 年末調整
- 社会保険
- 労働時間の計算
それぞれ解説していきます。
副業収入が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要
年間の副業収入が20万円を超えた場合は、所得税の確定申告をしなければなりません(20万円ちょうどであれば申告は不要)。なお、パートやアルバイトの収入は税金や保険料が引かれる前の金額、クラウドソーシングや業務委託で企業に所属せずに得た収入については、収入から経費を引いた金額が対象となります。
副業収入がある場合は住民税の申告が必要
副業で得た収入が1円以上20万円以下の場合は、住民税の申告をしなければなりません。
所得税の確定申告をする場合は、税務署と市町村が情報を共有しているため住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要となります。住民税の申告は、市役所の市税課や市税事務所の担当窓口へ必要書類を提出して行います。
なお、所得税がかからず住民税のみ発生する場合は、ふるさと納税を活用することで住民税の控除が受けられる可能性があります。
年末調整は1ヶ所で実施
副業をしている場合でも、年末調整を行うのは1つの勤務先のみです。複数の勤務先がある場合は副業の収入を本業の勤務先へ提出し、まとめて年末調整を受けなければなりません。これは、複数の勤務先で年末調整を行うと正しい税額が計算できないためです。
社会保険は1ヶ所のみ
健康保険や雇用保険などの社会保険は、加入条件を満たしている勤務先1ヶ所のみで加入できます。どちらも加入条件を満たしていない場合は、社会保険の加入は不要です。ただし、どちらの勤務先でも加入条件を満たす場合は、メインの勤務先を決めて年金事務所へ届出を出さなければなりません。
派遣社員の社会保険については、こちらの記事でも解説しています。
労働時間は合算で管理
労働基準法では、1日8時間以内、週40時間以内の法定労働時間が定められています。
副業を行う場合、労働基準法上の管理は企業ごとに行われますが、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、本業と副業の労働時間を合算して管理することが求められています。
例えば、勤務時間が勤務先Aで週に40時間、勤務先Bで週に10時間となった場合、法定労働時間の週40時間を超えることになります。
- 本業と副業の労働時間が合計で1日8時間・週40時間を超えた場合は割増賃金が発生する
- 割増賃金の支払には、労働契約の締結の順番が影響するとされている
- 後から雇用契約を締結した企業が割増賃金を支払うケースが多い
なお、労働時間の通算管理は、労働者本人の申告が前提となっています。企業側には他社での労働時間を強制的に把握する手段がないため、労働者が副業(あるいは本業が別にあること)を申告しなければ、実際の労働時間を合算することができません。そのため、企業の労務管理としては、副業届の義務化や労働時間管理の仕組みを整えることが重要です。
また、厚生労働省の「モデル就業規則」では、副業・兼業を行う労働者について、労働時間通算の対象となるかを確認し、他の企業での労働時間や労働契約の内容を把握することが推奨されています。
※労働時間を合算しないケース
労働基準法が適用されない働き方や、労働時間の規制を受けない業種については、労働時間を合算する必要がありません。労働基準法が適用されないものとしてはコンサルタントやフリーランス、労働時間の規制を受けない場合としては農業、畜産業、水産業などがあります。
参考:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月改定)
なお、この通算管理ルールは企業の労務管理において広く認識されているものの、企業側の負担が大きいことから、この制度の見直しを検討する動きも出てきています。今後の法改正や運用変更の可能性があるため、企業の人事・労務担当者は最新の情報を注視する必要があります。
派遣社員が副業するための注意点
派遣社員が副業する場合に、注意しておくべきポイントがあります。
就業規則を確認する
副業を始める前に、派遣会社および派遣先企業の就業規則を確認しましょう。派遣会社の就業規則は、登録時に確認します。派遣先企業の規則は、求人に「副業可」と明記されたものを選ぶか、派遣会社に確認を依頼するとよいでしょう。また「副業可」と明記されている場合でも、詳細なルールなどは派遣会社に問い合わせるとより確実です。
コンプライアンスは特に注意する
派遣社員が副業する場合、企業側としては情報漏洩のリスクに注意が必要です。本業の情報を副業先で使用するなど情報漏洩が発生した場合、企業へ大きな損害を与えたり信用失墜につながる可能性があります。
従業員の副業を認めている企業では、コンプライアンス対策として定期的にチェックや研修を行うことをおすすめします。
本業に支障のない業務を選ぶ
2つ以上の企業で勤務する場合、どちらの勤務先にも支障が出ないようにしなければなりません。就業日以外の勤務や、単発での仕事、在宅ワークなど、本業との両立が可能な業務を選びましょう。また、心身の負担を考慮し、柔軟なシフトや余裕を持った勤務時間を設定するなど、無理のない勤務スケジュールを組むことが大切です。
企業が派遣社員の副業で注意すべきポイント
政府が副業・兼業を推進し、厚生労働省の「モデル就業規則」にも副業・兼業の項が記されたことで、副業の可否を検討している企業は少なくないのではないでしょうか。そこで、企業が副業を認める場合に注意すべきポイントを解説します。
時間・健康・安全に配慮
企業側は、副業が本業(派遣先での業務)に支障をきたさないよう、派遣労働者の労働時間や健康、安全面に十分な配慮を行う必要があります。特に、長時間労働や体力的・精神的負担の大きい業務では、過重労働が健康に影響を及ぼすリスクがあり、副業による過労からミスや事故が発生した場合にはトラブルへと発展する可能性もあるため注意が必要です。
派遣元企業には、労働者派遣法に基づく安全配慮義務があり、派遣社員の健康管理を適切に行う責任があります。健康診断やストレスチェックを実施し、派遣社員の健康状態を把握するとともに労働時間の状況を適切に管理することが求められます。
ただし、派遣社員が副業の事実を申告しない限り、派遣元・派遣先企業ともに労働時間を完全に把握することは難しく、適切な管理が困難になるケースもあります。そのため、副業を行う派遣社員には、自身の健康状態に考慮し、企業へ必要な情報共有を行うことが求められます。企業側は派遣社員の労働状況を適切に把握し、双方が連携して管理を行うことがトラブルの防止につながります。
副業を禁止または制限できる場合
前提として、厚生労働省は「企業が労働者の就業時間外の活動を一律に制限することは認められない」との見解を示しています。しかし、副業を禁止する項目を就業規則に設けること自体は合法です。厚生労働省が公表している「モデル就業規則」には、過去の裁判例を参考にした規則が記されています。副業を禁止または制限するケースは、次のとおりです。
- 1. 労務提供上の支障がある場合
- 2. 企業秘密が漏えいする場合
- 3. 会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
- 4. 競業により、企業の利益を害する場合
モデル就業規則では、上記の禁止または制限するケースに該当する場合、届出書の提出を求めることが推奨されています。リスク回避のためには、就業規則に具体的な基準を明確に定め、派遣社員にも周知することが重要です。
派遣社員の副業は双方に支障のない範囲で可能
派遣社員の副業は法的に認められていますが、派遣会社や派遣先企業の就業規則に従う必要があります。副業を希望する場合は、本業に支障をきたさないよう健康や労働時間を自己管理することが大切です。また、確定申告や住民税についての知識を持っておくことも必要です。
企業側も、副業を許可する場合は労働時間や情報管理のルールを明確にし、安全な就業環境を整えることが求められます。
副業を含めた柔軟な働き方を支援しながら、企業の生産性を維持するためには、適切な人材配置が欠かせません。
アスマークの「Humap派遣」は、企業のプロジェクトを成功へ導くために最適な人材を紹介するサービスです。「人材の柔軟な活用」と「働きやすい環境の整備」の両立を目指し、派遣社員も柔軟に安心して働ける体制を整えてみてはいかがでしょうか。
100万人のアンケートモニターから
最適な人材をご提供
Humap派遣
執筆者

Humap編集局
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G