解雇規制の緩和とは?メリット・デメリットと企業の向き合い方
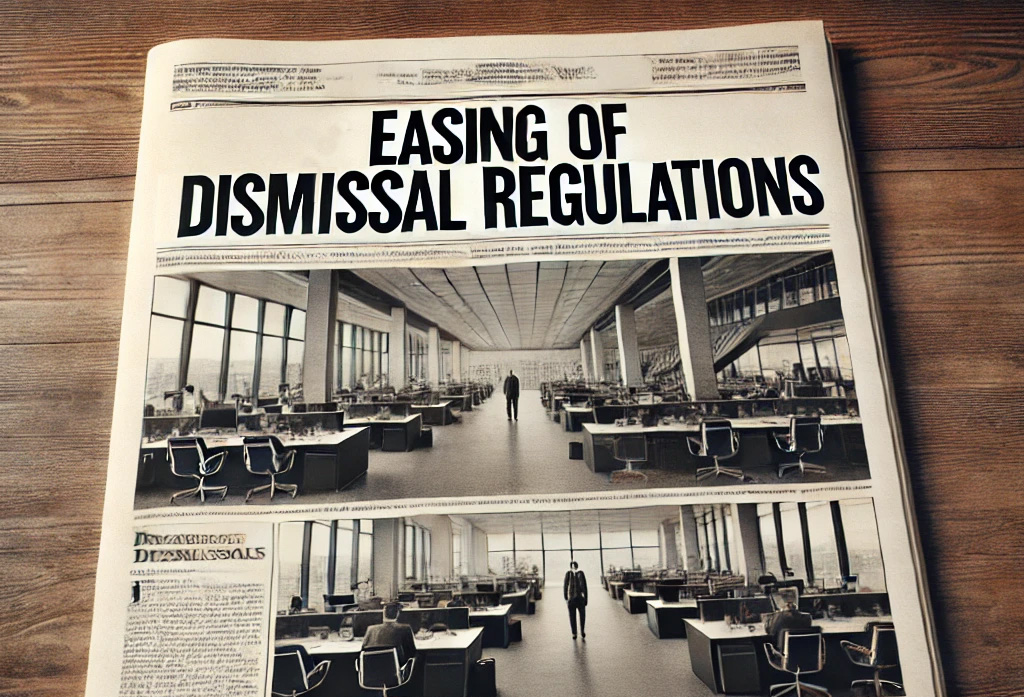
この記事を読む方の中には、「解雇規制が緩和されたら、どんな影響があるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
今回は、現在の解雇規制の概要や、緩和が進められた場合の企業および労働者への影響、将来的な労働環境の変化に備えて企業が取るべき対応について解説します。
解雇規制の緩和とは
解雇規制の緩和とは、労働者の解雇に関する法律や制度を見直し、企業が雇用調整をより柔軟に行えるようにすることを指します。
現在(2025年2月時点)、日本の労働法では、企業が労働者を解雇する際に厳格なルールが定められています。この規制を見直し、企業の雇用の柔軟性を高めるかどうかについて、さまざまな議論が交わされています。
解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは、企業が労働者を解雇する際に適用される法的ルールです。
労働契約において、企業と労働者は原則として対等な立場ですが、労働者の方が雇用関係において弱い立場になりやすいため、法律によって一定の保護が設けられています。
この解雇権濫用法理は労働契約法第16条に規定されており、企業が労働者を解雇する場合は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。
現状の解雇規制
日本の法律では、企業が労働者を解雇する際に、労働契約法第16条を遵守することが義務付けられています。
労働契約法 第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
参考:e-Gov 法令検索_労働契約法第十六条(平成十九年法律第百二十八号)
解雇が認められるためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 人員削減の必要性があること
- 解雇を回避するための尽力(配置転換や希望退職の募集など)
- 解雇対象者の選定基準が合理的であること
- 労働者に対し、十分な協議と説明が行われたこと
このように、解雇に厳しい条件が課されているため、日本では企業が容易に従業員を解雇することができません。
諸外国との比較
日本では解雇に慎重な姿勢が必要で、欧米諸国に比べると、解雇規制が厳しいと考えられる傾向にあります。
・アメリカ
アメリカでは「随意雇用(At-will employment)」が原則であり、企業は従業員を解雇しやすい環境にあります。ただし、人種・性別・年齢などの差別に基づく解雇は法律で厳しく禁止されており、また、州ごとに規制の厳しさが異なります。
・イギリス
イギリスでは、一定期間以上雇用された労働者に対しては不当解雇を防ぐための保護がある一方で、企業が解雇しやすくするための緩和策も導入されています。
「解雇」と「退職」の定義と種類
離職には、「解雇」と「退職」があります。ここでは、解雇規制に関係する主要な離職の種類について解説します。
整理解雇
整理解雇とは、業績の悪化や事業縮小など、企業の経営上の理由による解雇です。
企業は、解雇を回避するための努力を尽くした上で、合理的かつ社会通念上相当な理由をもって対象者を選定しなければなりません。解雇を行う場合、30日前までに予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払うことが求められます。
普通解雇
普通解雇とは、労働者の能力不足や勤怠不良、健康上の問題など、就業規則に基づく解雇のことです。企業は、解雇の正当性を確保するため、原則として指導や改善の機会を提供することが求められます。ただし、重大な非行などにより解雇の正当性が認められる場合は、即時解雇が可能なケースもあります。
希望退職
希望退職とは、企業が一定の条件を提示し、労働者の意思による退職を募る制度です。
一般的には、退職金の上乗せや再就職支援などが提供され、会社都合の退職として扱われることが多いですが、個別の合意内容によって異なる場合もあります。
早期退職
早期退職は、定年退職の年齢より前の時点で退職を促す制度です。企業のリストラ施策の一環として行われる場合と、キャリア形成支援として実施される場合があります。一般的に、整理解雇を回避するための早期退職は会社都合として扱われることが多いですが、企業が応募要件に自己都合退職とする条件を設ける場合もあり、扱いは異なります。
解雇規制の緩和が与える影響
解雇規制の緩和が行われた場合、企業と労働者にはどのような影響があるのでしょうか。それぞれのメリットとデメリットを解説します。
企業への影響
メリット
・人員配置の柔軟化
現在の厳格な解雇規制が見直されることで、解雇のルールが整理され、企業が適切な人員配置をしやすくなります。これにより、業績や事業の状況に応じて必要なスキルを持つ人材を確保しやすくなり、組織の最適化が進むことで生産性向上が期待できます。
・人件費の適正化
経営状況に応じて適正な人件費管理が可能になります。
デメリット
・従業員のモチベーション低下
解雇リスクが高まることで、従業員のモチベーションやエンゲージメントの低下が懸念されます。
・教育コストの増加
人材の流動化が進むと、新入社員の育成コストが増大します。
解雇規制が緩和された場合、企業にとっては解雇がしやすくなる反面、優秀な人材の流出も懸念されるため、従業員が魅力を感じる職場づくりがこれまで以上に求められるといえるでしょう。
また、解雇規制が緩和されたとしても、解雇の正当性をめぐる裁判が起こる可能性は引き続きあります。企業がいつでも自由に従業員を解雇できるようになるわけではない点には注意が必要です。
労働者への影響
メリット
・転職の自由度が高まる
労働市場の流動性が向上し、キャリアの選択肢が広がるほか、自分に合った企業や仕事が見つけやすくなります。また、企業が解雇をしやすくなることで、求職者にとって新しい雇用機会が生まれる可能性もあります。
デメリット
・雇用の不安定化
企業側が解雇をしやすくなるため、解雇への不安から精神面や生活に影響が出る可能性や、長期的な雇用の安定性が失われる可能性があります。
解雇規制の緩和に向けた企業の対応とは
仮に今後、解雇規制の緩和が進んだ場合、従業員の動揺や退職者の増加が懸念されます。そのため、企業は労働環境の整備や適切な情報を通じて、従業員の不安を軽減する対応が求められます。規制が緩和された場合に備えて、どのような対策を考えておくべきでしょうか。
従業員への説明
法律の変更があった場合、企業は従業員に対して新しい解雇ルールや影響を明確に説明することが求められます。企業ごとの解雇基準や手続きを整理してわかりやすく説明することで、不安を軽減できます。また、解雇に関する誤解を防ぐため、社内Q&Aやガイドラインを整備し、従業員がいつでも必要な情報にアクセスできるようにしておくとよいでしょう。従業員が持つ疑問や懸念と丁寧に向き合い、信頼関係を維持することが大切です。
労働環境の整備
解雇規制が緩和された場合、労働市場の流動性が高まることで、人材の確保と定着がより重要になります。そのため、評価制度や給与の透明性を高め、公正な基準を設けることが必要です。また、従業員が「この会社で働き続けたい」と感じられるよう、キャリア形成や福利厚生の充実にも注力したいところです。
加えて、社内コミュニケーションの活性化や、心理的安全性の確保を意識することで、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上につながるでしょう。
離職を防ぐための人事施策をまとめた資料を無料で提供しています。合わせてご覧ください。
キャリア支援
企業は従業員のキャリア形成を積極的に支援することが求められます。具体的には、リスキリング(学び直し)やキャリアアップの機会を提供することが有効です。キャリア相談窓口を設け、従業員が将来の働き方について相談できる環境を整えることも重要でしょう。
また、アルムナイ採用(退職者の再雇用)の活性化も想定されます。企業と従業員の良好な関係を維持し、柔軟な雇用の仕組みを確立することが期待されます。
リスキリングについては、導入を検討している企業に向けて取り組みのポイントをまとめた資料を配布しています。こちらも合わせてご利用ください。
リスクマネジメント体制の整備
解雇規制の緩和によって、解雇の正当性をめぐるトラブルが増加する可能性があります。
これに備え、企業は労務リスクの管理体制を強化し、解雇に関する判断基準や社内ルールを明確にしておきましょう。また、万が一のトラブルに備え、法律の専門家(弁護士・社労士)と連携し、リスク対策を講じておくことも有効です。
選ばれる企業になるためには「ASQ」
現在の日本では、解雇規制の緩和について議論がされている最中ですが、具体的な法改正などは決まっていません(2025年2月現在)。企業に求められるのは、今後の動向を注視しながら、働きやすい環境を整えることです。
しかし、企業が自らの労働環境の課題を正確に把握し、その改善策を講じることは容易ではありません。
そこで役立つのが、従業員満足度調査(ES調査)を活用した職場環境の改善です。
アスマークの「ASQ」は、調査結果を基に、離職リスクの分析や組織改善のポイントを明確にし、具体的な改善施策の提案もセットになった従業員満足度調査サービスです。
施策提言まで込みの
真に役立つES調査パッケージ
ASQ
将来の労働環境の変化に備えて、従業員満足度調査を活用した労働環境の改善を検討してみてはいかがでしょうか。
執筆者

Humap編集局
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G












