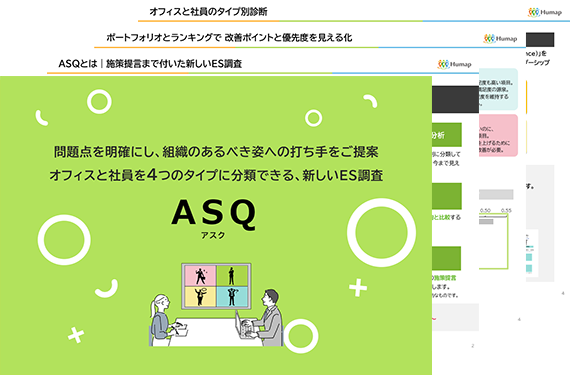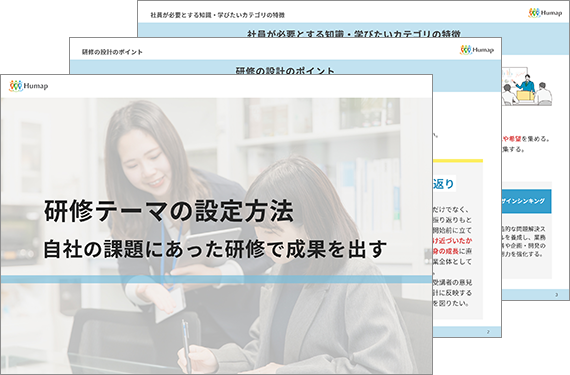従業員満足度調査の結果を活用して研修を計画しよう

この記事を読む方の中には「ES調査を実施しているが、形骸化していて意味がなくなってきている」と気になる方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、従業員満足度調査の活用についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
従業員満足度調査とは?
従業員満足度調査とは、自社の従業員を対象に、業務や人間関係、職場環境などの満足度を把握できる調査です。 英語で従業員満足度をあらわす「Employee Satisfaction」の頭文字を取って「ES」調査とも呼ばれています。
近年、少子高齢化による人材不足から、厚生労働省も魅力ある企業作りを重視しています。従業員が魅力を感じている組織は、離職率が低く、生産性の向上も見込めるため、より強い組織を作ることを目的として調査を実施する企業も増えているようです。
従業員満足度調査の活用法
従業員満足度調査の具体的な活用例をご紹介します。
評価制度の見直し
評価や給与の制度に公平性を感じられなければ、「頑張っても評価されない」と従業員の士気が下がってしまう恐れがあります。調査結果で判明した課題に応じて評価や給与の制度を見直すことができます。上司からの説明不足による不公平感の場合は、管理職の研修などで対策が可能です。
職場環境の改善
オフィススペースや多様な働き方など、労働環境に関する項目を設問に入れておくと、職場環境の改善に活用できます。職場環境に関する設問は、備品やスペースなど多岐に渡るため、課題を把握したいのであれば、細かい設問を作るか自由記入欄を設けるのがおすすめです。 調査結果を職場環境の改善に活用している例をご紹介します。
コミュニケーションの活性化
同僚や上司など、職場の人間関係の活性化にも調査の分析結果を活用できます。部下との関係性に悩む管理職や上司への接し方に悩む部下など、全員へ情報を共有すると、双方のニーズが確認できるでしょう。 テレワークが多く、従業員同志のコミュニケーションが取れないと悩む場合は、オフィスにモニターを設置して顔を出すなどの対策が取れます。 従業員満足度の分析結果をコミュニケーション活性化に活用している例をご紹介します。
従業員のメンタルケア
満足度の低い従業員の割合により、メンタルケア不調の早期発見に効果的です。メンタルに関するスコアが低い場合は、産業医との定期面談やリラックスできるスペースを設けるなどの対策ができます。
生産性の向上
人間関係や職場環境、評価制度に至るまで、満足度に関わるさまざまな要因がモチベーションに影響します。個人の価値観は多様です。誰が何に対して満足するか分かりません。不満の内容と度合いによって、モチベーションが下がり、生産性が低下します。 調査結果を見て、多くの従業員が不満に感じている要因から改善に取り組めば、従業員のモチベーションが向上し、組織全体の生産性の向上も期待できるでしょう。
採用活動でのアピール
従業員満足度の高い企業は、求職者から見ても魅力的です。満足度の高さを求職者へアピールすることで、自社アピールできます。
また満足度の高い項目は自社の強みにもつながってくるため、満足度から得た強みを前面に打ち出すなど採用コンセプトなどの参考にもできます。
課題の把握
改善すべき課題が全く思いつかない場合においても、従業員満足度の活用が可能です。従業員満足度調査の設問は、職場環境や人間関係などのカテゴリに分かれています。自身では気付きづらい従業員の不満も細かく分析することができます。見えづらい現場社員の不満など組織全体に潜んでいる課題に気付くことができるのが従業員満足度調査の特徴です。普段口には出しづらい悩みや不満も匿名のアンケート形式であれば本音を引き出せるケースもあります。
施策の改善度を把握
調査は、実施中の施策がどの程度改善しているかを確認するためにも活用が可能です。改善度を把握するには、同じカテゴリの設問を含めて調査を実施し、経年でスコアを比較します。スコアの改善度により施策に効果があったのか図ることができ、次年度以降の施策検討の材料にすることもできます。
施策の改善に活用している例をご紹介します。
研修テーマの設定
調査結果で判明した自社の課題に合わせ、研修カリキュラムを計画するなど従業員満足度調査の結果は人材育成の参考にもできます。課題を事前にする合わせることができれば、より充実した研修を実施できます。
すでに実施しているコンプライアンスやハラスメント研修があれば、その理解度や対策の浸透具合なども把握が可能です。理解が進んでいるようであればより実践的な内容で研修を実施する等検討にも活用可能です。
従業員満足度調査で自社の弱みを発見できれば、研修テーマの設定やカリキュラムの見直しに活用できます。
研修テーマをあぶり出せる調査サービスをアスマークで提供中です。ぜひご活用ください。
参考:組織・個人のハラスメントリスクが分かる「CHeckリサーチ」
結果を有効活用できる調査のポイント
結果を有効活用するには、3つのポイントを意識した調査をしましょう。
- 自社の課題や施策の活用を踏まえた設問設計
- ベンチマークデータとの比較
- 経年変化を分析
調査を実施するにあたり、コストを抑えるために社内での実施を検討するケースもあるかと思います。
ネットで探したテンプレートなどからそのまま設問を引用してしまうと、自社の実態や課題に合っていなく従業員の不満が引き出せなかったり、本音を引き出せず施策に落とし込めない結果となってしまうなど、意味のない調査になってしまう恐れがあります。
日頃の課題や実施予定の施策など、明確な目的を持って設問を設計すると、データを分析しやすくなります。そもそも自社の課題が分からない場合は、幅広い調査も検討すると良いでしょう。
分析しやすい設問設計を求めるのであれば、外部の専門家への依頼をおすすめします。アスマークが調査の分析で使う1万人のベンチマークデータを毎年更新しています。ベンチマークデータとは年代や同業など、比較対象となるデータのことです。同業と比較できると、アピールできる魅力や改善すべき課題が明確になります。
また継続して調査を行うことで経年変化を見ることができます。経年変化は、施策の改善度や従業員の傾向を知るために活用可能です。
有意義な調査のためには、データ活用を踏まえた設問設計と、比較できるデータの準備がポイントです。設問とデータ分析によって課題を可視化し、その後の施策提言までわかるアスマークの従業員満足度調査のレポートサンプルをご紹介します。
従業員満足度調査を活用して充実した研修にしよう
従業員満足度調査とは、業務や人間関係、職場環境など、従業員の満足度を可視化するための調査です。少子高齢化による人材不足から、厚生労働省も従業員満足度調査の実施を推進しています。 調査結果は、評価制度の見直しや職場環境・人間関係の改善、課題の洗い出しへの活用が可能です。洗い出した課題から、研修テーマを決めると、有意義な研修が実施できます。
調査をしても、どの課題から着手すべきかわからない、どんな研修・施策に重きを置くか悩むという場合は、アスマークの「調査+研修」がパッケージ化されたES+がおすすめです。
ES+では調査から分かった課題に合わせ、50種以上の研修からテーマをオーダーメイドでプランを設計します。組織の課題の根本解決に向け徹底した伴走支援を行ってます。
「調査+研修」で
働きやすい職場環境づくりを
ES+
調査結果を有効活用するためには、課題や活用を意識した設問設計とベンチマーク・過去の結果など、比較できるデータの準備がポイントです。
調査データを有効活用して、魅力ある組織を目指しましょう。